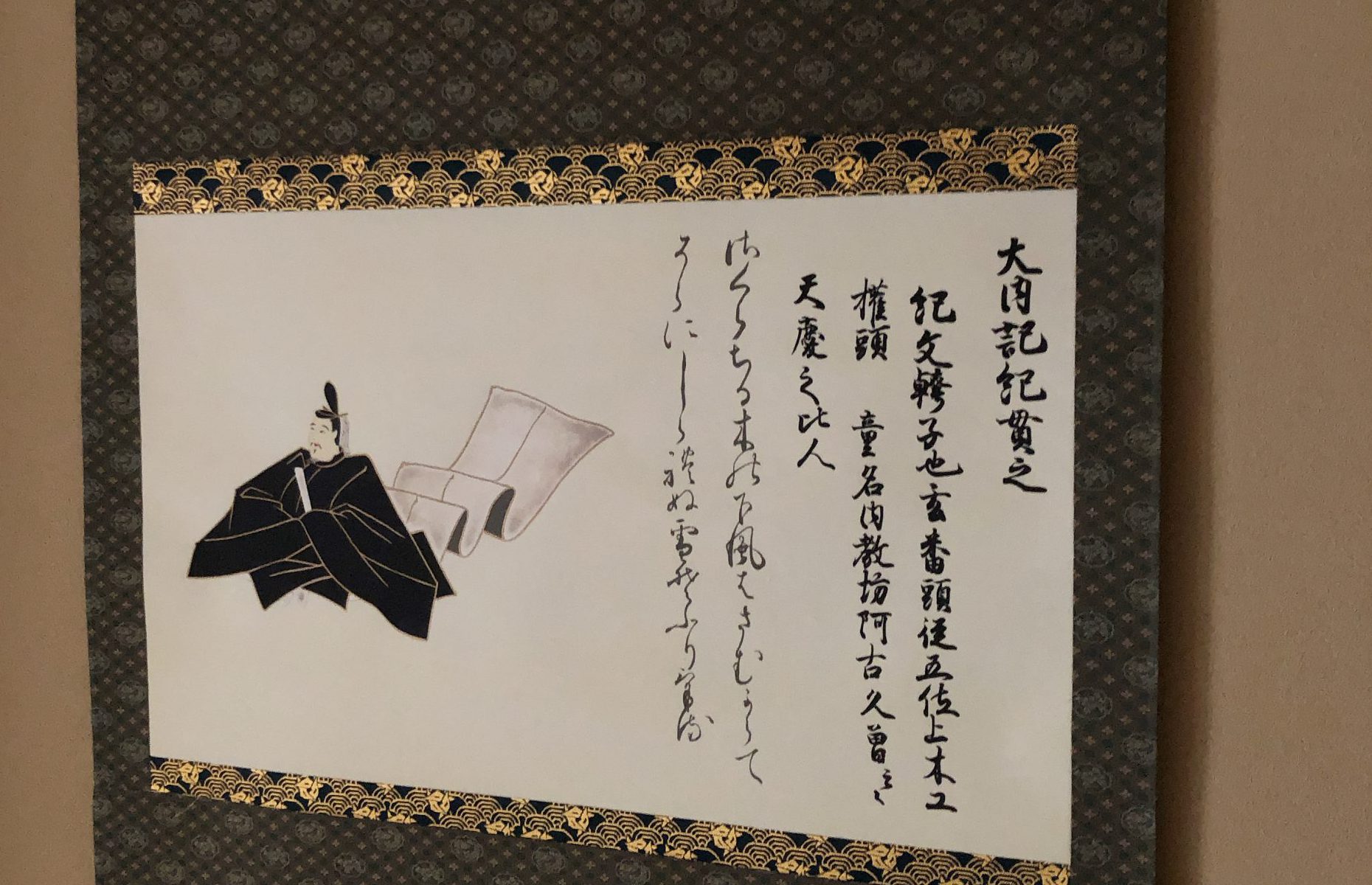今年もいよいよ最後の月となりました
12月は師走とも申しますが、臘月(ろうげつ)とも呼ばれます
その1日から8日までの間は臘八摂心といって、禅寺では厳しい修行の期間となります
暖冬といえど、やはり凍てつく空気の中、寝ずの座禅の厳しさに、思いを馳せるだけでもこちらも身が引き締まるような気がいたします
わが家の稽古では、冬ならではの浦千鳥水指を使ったお点前や、運びのお点前、さらには伝ものの四ヶ伝などを予定しています
炉とご自身の体のサイズとの関係から導き出された、絶妙な位置関係を、このひと月で掴み取っていただければと存じます
もう年末、されどひと月
忙しない日常に頭はフル回転ですが、茶室の中で、ただ季節を感じるだけの時間を持つことができるのは、幸せなことだと思います